活動記録-2017年(平成29年)
「古文書にみる長岡のすがた」第1回を開講しました!
8月23日(水)、経験者向け古文書解読講座「古文書にみる長岡のすがた」第1回が開催されました。テーマは「牧野家の長岡入部と家臣団」、講師は文書資料室の田中洋史室長です。悪天候の中、58名の方の参加がありました。
今回は、文書資料室所蔵の「懐旧雑誌」等いくつかの“古記録”から、稲垣家や山本家、贄(にえ)家など長岡藩の家臣団について、経歴や家格・居住地を探りました。
今年度の講座では、来年の長岡開府四百年にちなみ、長岡藩にまつわる古文書をテキストに使用しています。長岡藩の歴史を学ぶ絶好の機会となるに違いありません。


今回は、文書資料室所蔵の「懐旧雑誌」等いくつかの“古記録”から、稲垣家や山本家、贄(にえ)家など長岡藩の家臣団について、経歴や家格・居住地を探りました。
今年度の講座では、来年の長岡開府四百年にちなみ、長岡藩にまつわる古文書をテキストに使用しています。長岡藩の歴史を学ぶ絶好の機会となるに違いありません。


長岡市史双書を読む会(3)を開催しました
7月26日(水)、「長岡市史双書を読む会」の第3回講座を開催しました。最終回となる今回は、長岡市史双書No.56『近代長岡の雑誌(2)『温古の栞』と大平与文次・温古談話会』の中から、名所旧跡の部をテキストに、当室の岡田佐輝子専門研究員が講師を務めました。
はじめに『温古の栞』の名所旧跡の部について概説したあと、貴族や天皇の皇子にまつわる旧跡や池の伝説、与文次の故郷・越路の河川の記事をとりあげ、解説を行いました。画像をまじえた身近な地域の話に、みなさん熱心に聞き入っていました。
みなさま『温古の栞』の世界を楽しんでいただけたでしょうか。今年度の長岡市史双書を読む会も盛況のうちに幕を閉じました。来年度もよろしくお願いいたします。


はじめに『温古の栞』の名所旧跡の部について概説したあと、貴族や天皇の皇子にまつわる旧跡や池の伝説、与文次の故郷・越路の河川の記事をとりあげ、解説を行いました。画像をまじえた身近な地域の話に、みなさん熱心に聞き入っていました。
みなさま『温古の栞』の世界を楽しんでいただけたでしょうか。今年度の長岡市史双書を読む会も盛況のうちに幕を閉じました。来年度もよろしくお願いいたします。


『温古の栞』で探る戦国時代の山城とその魅力
7月12日(水)、「長岡市史双書を読む会」の第2回講座を開催しました。長岡市史双書No.56『近代長岡の雑誌(2)『温古の栞』と大平与文次・温古談話会』をテキストに、新潟県文化財保護指導委員の鳴海忠夫さんが講師を務めました。
講座は長岡市内に所在する戦国時代の山城と居館の分布状況を概観したうえで、『温古の栞』の「古城跡の部」の記事と実際の遺構を比較しながら進められました。栖吉城や栃尾城など、実際に踏査して作成した縄張図と『温古の栞』の記事との比較は具体的で興味深く、参加者一同、山城研究の魅力に引き込まれていきました。
第3回(最終回)は「名所旧跡の部」がテーマです。7月26日(水)に開催します。引き続きご参加ください。

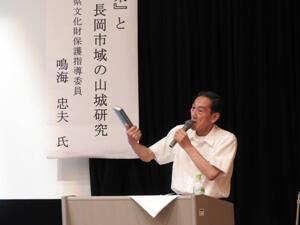
講座は長岡市内に所在する戦国時代の山城と居館の分布状況を概観したうえで、『温古の栞』の「古城跡の部」の記事と実際の遺構を比較しながら進められました。栖吉城や栃尾城など、実際に踏査して作成した縄張図と『温古の栞』の記事との比較は具体的で興味深く、参加者一同、山城研究の魅力に引き込まれていきました。
第3回(最終回)は「名所旧跡の部」がテーマです。7月26日(水)に開催します。引き続きご参加ください。

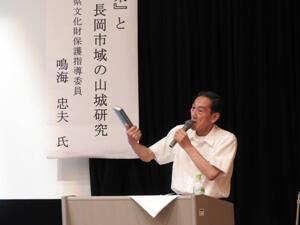
長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました
7月13日(木)、長岡市資料整理ボランティアの活動を行いました。場所は互尊文庫3階の学習室です。25名の方が参加し、新聞資料整理と古文書整理に分かれて活動を行いました。
新聞資料整理は全国紙から新潟版を切り抜く作業を行いました。古文書整理は、前回に引き続き金子家の年貢割付状の目録取りを行い、70点を整理しました。皆さん、お疲れさまでした。
長岡市資料整理ボランティアは随時メンバーを募集しています。文書資料室までお気軽にお問い合わせください。
長岡市資料整理ボランティア募集ちらし.pdf


新聞資料整理は全国紙から新潟版を切り抜く作業を行いました。古文書整理は、前回に引き続き金子家の年貢割付状の目録取りを行い、70点を整理しました。皆さん、お疲れさまでした。
長岡市資料整理ボランティアは随時メンバーを募集しています。文書資料室までお気軽にお問い合わせください。
長岡市資料整理ボランティア募集ちらし.pdf


「長岡市史双書を読む会」が始まりました!
7月5日(水)、「長岡市史双書を読む会」の第1回講座を開催しました。長岡市史双書最新刊のNo.56『近代長岡の雑誌(2)『温古の栞』と大平与文次・温古談話会』をテキストに、田中洋史文書資料室長が講師を務め、100名を超える皆様からご参加いただきました。
三島郡浦村(長岡市越路地域)出身の大平与文次が中心となり、明治23年から3年間、36篇まで発行された雑誌『温古の栞』を取り上げ、郷土史研究の黎明期を飾るその全体像や、温古談話会の活動について解説しました。
第2回(7月12日)は「戦国時代の山城」、第3回(7月26日)は「名所旧跡」がテーマです。連続3回の講座をぜひお楽しみください。


三島郡浦村(長岡市越路地域)出身の大平与文次が中心となり、明治23年から3年間、36篇まで発行された雑誌『温古の栞』を取り上げ、郷土史研究の黎明期を飾るその全体像や、温古談話会の活動について解説しました。
第2回(7月12日)は「戦国時代の山城」、第3回(7月26日)は「名所旧跡」がテーマです。連続3回の講座をぜひお楽しみください。


