活動記録-2014年(平成26年)
リレー講演会「災害史に学ぶ」第4回
第4回講演会の演題は「文政大地震と与板」、講師は新潟県立巻高等学校長の本田雄二さん、会場はよいたコミュニティセンターです。
講師の本田さんは、平成11年に刊行された『与板町史』の編集・執筆委員として、江戸時代の与板地域に関する調査・執筆を担当され、編集紀要『町史よいた』第1集に「文政大地震と与板」を発表しています。
約90名が参加した講演会では、文政11年(1828)に発生し、現在の三条市、見附市、長岡市などに甚大な被害を及ぼした地震における与板地域の被害と救済を中心に、良寛が生きた時代の大震災にせまりました。
リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。
参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。




長岡市史双書を読む会 第3回開催
文書資料室の桜井奈穂子嘱託員が講師を務め、「海岱日録~詩画の娯を成す旅①」と題し、江戸時代の旅日記を読み解きました。
「海岱日録」は、村役人・清水雪海と長岡藩士・小林誠斎(虎三郎の父)の旅の記録です。
今回の講座では、旅立ちから善光寺・伊勢・大坂までの日記を読み進めました。
旅路の風景や様々な人々との出会いなどが綴られており、ユーモラスなエピソードに、会場が笑いに包まれる一幕もありました。




リレー講演会「災害史に学ぶ」第3回
第3回講演会の演題は、「日本政治史の中の大竹貫一~大竹邸記念館史料の「発見」と保存~」、講師は東京大学先端科学技術センター協力研究員の佐藤健太郎さんです。
会場の中之島コミュニティセンターは講演会開催日に誕生祭を開催中。
講演会には125名の参加がありました。
講師の佐藤さんは、岩手県出身。
東京大学法学部卒業後、平成24年に東京大学大学院で博士号を取得し、日本政治史の研究と歴史資料の保存に取り組む、気鋭の研究者です。
講演会では、佐藤さんが今年3月まで在籍していた東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター原資料部による大竹邸記念館所蔵資料をマイクロフィルム化した成果をふまえつつ、治水事業に尽力した中之島地域出身の政治家・大竹貫一の人物像にせまりました。
なお、当日は講演前に大竹邸記念館所蔵資料のマイクロフィルム受贈式も開催しました。
東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター原資料部の國分航士さんより、中之島支所長にマイクロフィルムが手渡されました。
リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。
参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。




リレー講演会「災害史に学ぶ」第2回
第2回講演会の演題は、「「八犬伝」にみる二十村の世界~災害に負けない山のくらし~」、講師は元山古志村史編集委員の滝沢繁さん、会場はやまこし復興交流館おらたるです。
滝沢さんは、『山古志村史』通史で近現代の歴史の調査・執筆を担当されました。
中越大震災発生後は、山古志地域の文書資料の保全活動に取り組み、種苧原地区出身で小説『野分』(夏目漱石/著)の主人公のモデルとして知られる教育者・坂牧善辰に関する研究を進めています。
講演会には約60人が参加し、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』に描かれた「牛の角突き」を中心に、かつて「二十村」(にじゅうむら)と呼ばれていた山古志地域の歴史と文化、そして、震災復興に向けた取り組みについて学びました。
リレー講演会「災害史に学ぶ」は、12月まで開催しています。
参加は随時受付中ですので、詳細は下記からご覧ください。

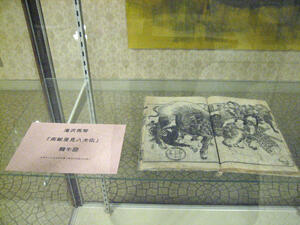

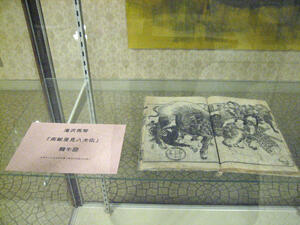
新潟県立文書館で7.13水害避難所資料を展示中!
平成16年7月13日に発生した7.13水害(新潟・福島豪雨)からまもなく10年を迎えます。
新潟県立文書館(新潟市中央区)では、常設展示「平成16年7月新潟・福島豪雨「7.13水害」から10年~記録が伝える災害の記憶~」を開催しています。
長岡市が所蔵する歴史資料から、7.13水害の避難所資料を中心に、中越大震災、東日本大震災の避難所運営に関する資料などを展示しています。
会期は、7月27日(日)までです。
ぜひ、足をお運びください。



